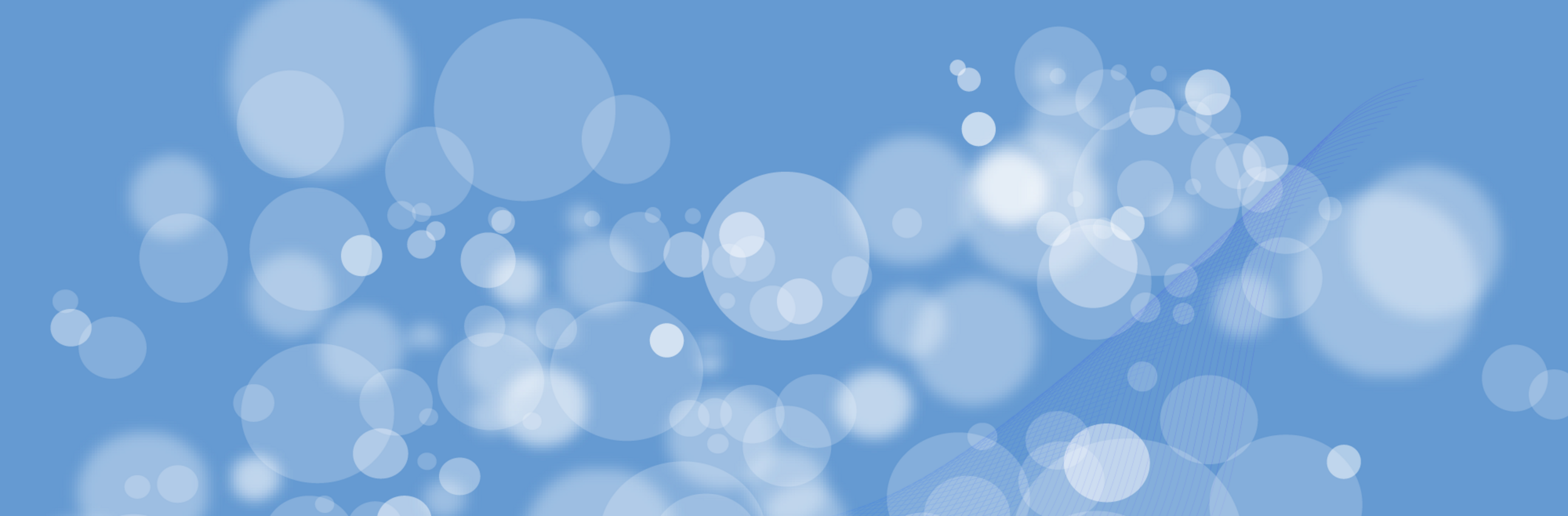
「粒子軌跡解析法」は比較的新しい測定原理ですが、その方法自体は非常に単純でわかりやすいものです。この手法では動的光散乱法と同様に、粒子のブラウン運動を測定します。動的光散乱法が散乱光強度のゆらぎでブラウン運動を測定するのに対し、粒子軌跡解析法では実際にカメラを用いてブラウン運動をしている粒子を輝点として観察します。
溶媒中の粒子にレーザー光を照射すると、粒子によって光が散乱されます。レーザー光の光軸に対し、直角の方向からカメラで観察すると、粒子が輝点として観察されます。測定対象となる粒子は、光学的な分解能よりも小さく、輝点の大きさからでは粒子径はわかりません。しかしながら、この輝点がブラウン運動によりランダムに動き回る様子を観察することができます。したがって動画を取得し、1 フレームごとに粒子がどこに移動したかの軌跡を追跡することで、ブラウン運動の変位(速度)を算出できます。
ある1 つの粒子の平均二乗変位(MSD:mean square displacement)は、下記のように計算されます。
\(MSD(n)=\frac{1}{N-n}\displaystyle\sum_{i=1}^{N-n} \begin{pmatrix}x_{i+n}-x_i \end{pmatrix}^2+\begin{pmatrix}y_{i+n}-y_i \end{pmatrix}^2\)
このとき、画像の枚数は全部でN 枚あり、ある画像での粒子の位置(xi, yi) が、n 枚後の画像では位置(xi+n, yi+n) に移動しています。二次元モデルでは、1 枚当たりの時間差をΔt とすると、平均二乗変位は拡散係数D を用いて下記の式で表すことができます。
\(MSD(n)=\begin{pmatrix}4\Delta{tD}\end{pmatrix}n\)
拡散係数D が得られれば、温度と粘度の情報を用いることで、粒子径は動的光散乱法と同様に、ストークス・アインシュタインの式で算出されます。
\(d=\frac{k_BT}{3πηD}\)
この計算により 1 つの輝点に対する粒子径が算出されます。同様に観察された輝点に対して粒子径を算出していき、個数を数えることで粒度分布が得られます。したがってこのとき得られる粒度分布は、粒子径として拡散係数相当径、粒子径基準として個数基準のものとなります。
この手法も、動的光散乱と同様にブラウン運動を基準とした粒子径の分析方法であるため、ナノ粒子に特化した分析方法です。
粒子を1つずつカウントして粒度分布を作るため、縦軸が絶対値となり、個数濃度の情報が得られることが最大の特徴です。また集団を一度に分析するのではなく、粒子を 1 つずつ分析するため、分解能も高いものとなります。最適な濃度で分析を行えば、1 つの視野で 100 個程度の粒子を観察できます。粒子をいくつ観察するかによって測定時間は変わりますが、レーザー回折 / 散乱式や動的光散乱法に比べると、測定に要する時間は長くなります。
また大きい粒子は強い散乱光を、小さい粒子は弱い散乱光を発するため、大きさが異なる粒子を同時に分析するには、小さい粒子が観察できる散乱光強度を得つつ、強い光でも点として観察できる必要があります。このため 1 種類の波長の レーザー光源だけを持つ装置では、分析できる粒度分布の幅は狭くなります。
ナノ粒子径分布・濃度測定装置ViewSizer 3000 と典型的な測定例
ナノ粒子径分布・濃度測定装置 ViewSizer 3000は、特徴で述べた測定レンジの狭さという弱点を克服しています。ViewSizer 3000では、青色、緑色、赤色の 3本のレーザーを同軸に揃えて粒子に照射し、それをカラーカメラで観察します。カラーカメラでは、1つの画素(フルピクセル)に3色それぞれに感度を持った画素(サブピクセル)が含まれています。こうして1つの粒子を同時に 3色で観察できるため、小さい粒子は青色で、中くらいの粒子は緑色で、大きい粒子は赤色で分析することができます。
実際に、3 色に分けた画が下記です。 左図では、小さい粒子が存在している箇所ですが、青色では観察できている一方で、赤色では観察できていません。 青色の情報を用いることで、赤色だけでは取得できなかった小さい粒子の情報が得られています。右図では大きい粒子が存在している箇所ですが、赤色では点として観察できている一方で、青色では強度が強すぎて、粒子の存在している位置が特定できなくなります。
左図
右図
照射した光の波長以外の波長で光る粒子(蛍光粒子)を分析することも可能です。入射光の波長をカットするフィルターをカメラの前に設置することで、散乱のみを起こしている粒子は見えなくなり、蛍光を発している粒子のみを観察できます。これにより、特定の蛍光マーカーが付いた粒子のみの粒子径と個数濃度を分析することができます。例えばエクソソームなどのバイオマテリアルでは蛍光標識されたもののみを分析することで、夾雑物の情報に影響されない分析が可能です。
HORIBAは、「Your Partner in Science」をテーマにオンラインセミナーで、各種分析の基礎やノウハウを紹介しています。皆様からのご視聴お申込みを心よりお待ち申し上げております。
粒子計測、蛍光X線分析、元素分析、分光分析、ラマン分光分析、蛍光分光分析、表面分析の基礎やノウハウを紹介したセミナー(アーカイブ動画)の一覧です。